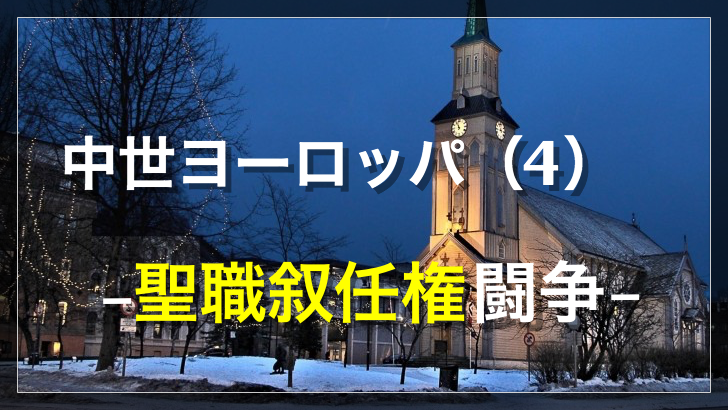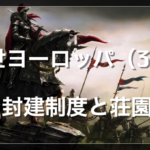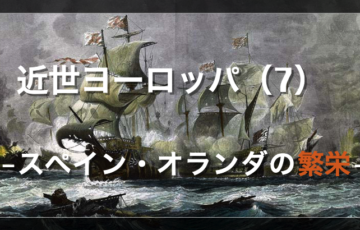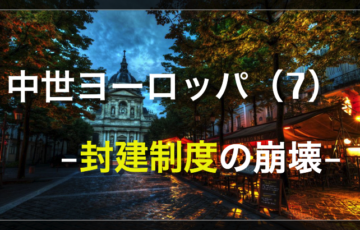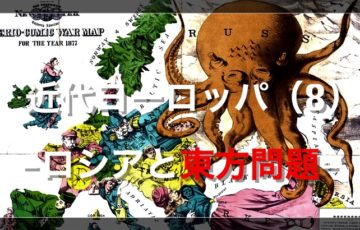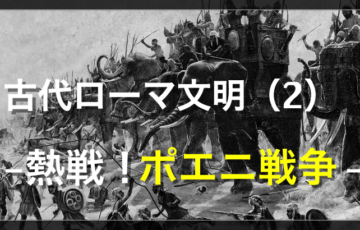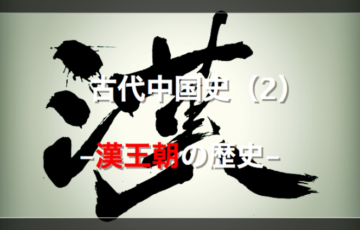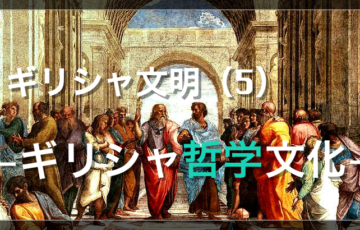教会と権力
さぁ今回は、教会と権力のお話です!権力が絡むと宗教はブラックです!(笑)
まずおさらいですが、ローマ=カトリックとはローマ帝国時代にニケーア公会議で認められたアタナシウス派のことを指します。
しかしローマ帝国分裂後は、主に西と東で教会が対立し分離してしまいます。
果たしてどちらが権力を握ることになるのでしょうか?そしてその後にもドラマがあります。
ローマ=カトリック教会とコンスタンティノープル教会の対立・分裂
東西に分裂してしまった2つのキリスト教教会。
片方は西側のローマ=カトリック教会、もう片方は東側のコンスタンティノープル教会です
(もともとは五本山と呼ばれるように、キリスト教教会は5つあったのですが7cに残り3つはイスラム圏に取り込まれてしまいます)
その両者の対立が決定的となったのは、東側のビザンツ帝国が726年に発した聖像禁止令です
7cにムハンマドが始めたイスラム教は急激に勢力を拡大し、大きな力を持っていました
イスラム教の代表的な教義は、偶像崇拝の禁止です
そしてイスラーム圏と地理的に近かったビザンツ帝国は、当然イスラーム教徒から聖像を作るのを禁止しろと圧力を受け続けるわけです。その煽りを受けて聖像・聖画像の崇拝を禁止する聖像禁止令をレオン3世(レオ3世と呼ばれる場合もある)が発布しました。
一方のローマ=カトリック教会はというと、ヨーロッパ北方にいる蛮族ゲルマン人たちになんとかキリスト教を布教できないかと試行錯誤していました。
ゲルマン人の多くは文字が読めなかったので、聖書を読ませてキリスト教の素晴らしさを伝えることが難しかったからです。
そこで思いついたのが聖像・聖画像の使用です!絵や彫刻なら見ただけで意味がピンと来るので布教には非常に便利です。そこで、ローマカトリック教会ではバンバン聖像を使用していました。
このキリスト教の布教にあたって聖像を用いてよいか否か?の議題で東西教会は厳しく対立!
1054年に互いに破門し合い、2つの教会は仲違いで終わります(なお聖像禁止令は843年には解除されるのですが・・・)
グレゴリウス7世とハインリッヒ4世の聖職叙任権闘争
さて、お話はローマ=カトリック教会に移ります。
教会の東西分裂後、西側のローマ=カトリック教会は腐りきっていました!
本来の聖職者とは、世俗との関わりを絶ちつつ一般人の霊的な生活を支援、つまり天国へと行けるように民衆の生活を指導する存在です。
しかし当時の聖職者たちは妻を娶りまくってやりたい放題、荘園を保有して領主となり世俗権力に介入したり、聖職者としての地位を売買したりともうヒャッハー状態です
そんな状況に異を唱えた教皇こそ、改革派の教皇グレゴリウス7世です。彼はクリュニー修道院の出身でした。
なぜここで教会と関係ない修道院が出てくるのでしょうか?
そもそも修道院の存在意義って何かわかりますか?教会と何が違うのでしょう?

修道院は、俗世間と関わらざるをえない聖職者たちとは対照的に、一般世界とは一切関わらない、閉ざされた空間の中で神への祈りと自給自足の生活を貫く存在です。
要は聖書通りの生活をおくる修行僧のようなものです。
そんな修道院の始まりは、ベネディクトゥスが6cに始めたベネディクト派の修道院です。
そこでは「祈り、働け」をモットーに厳しい生活を送り、やがて西欧全ての修道院を統括するまでに至る修道院のTopです。
そんなベネディクト派の修道院のうちの1つクリュニー修道院に11c、神聖ローマ帝国の皇帝からお達しが来ます。
「在俗聖職者・教会の腐敗を、修道院のノウハウを活かしてなんとかしてくれ。その代わり、ローマ教皇にしてあげるからさ」
まぁ、だいたいこんな感じです(笑)
世俗と関わりすぎて腐ってしまった聖職者たちを、世俗と隔離された生活に馴染んだ修道士に指導させればなんとかなるやろ!という軽い気持ちで、クリュニー修道院出身の者たちが教皇になることを皇帝は支援しました
そのうちの一人がグレゴリウス7世で、その人格者すぎる性格が災いして大波乱を巻き起こします。
グレゴリウス7世がやろうとしたことは聖職者の風紀刷新と世俗権力の排除です。
聖職売買の禁止、聖職者の妻帯を禁止するなど風紀の刷新は一応事無く進みました。
が、世俗権力の排除はそう上手くはいきません。
当時の神聖ローマ帝国では、帝国下での教会に対しての聖職者の叙任権、つまり誰を聖職者に選ぶかの権利は神聖ローマ皇帝が担っていました。
しかし、グレゴリウス7世は世俗権力の象徴である皇帝が聖職者を任命することこそが聖職売買の元凶なのだと厳しく批判し、聖職者の叙任権は世俗と袂を分かつ教皇にこそあるべき!と主張しました
当然、皇帝側がそんな主張を認めるわけもなく、神聖ローマ皇帝ハインリッヒ4世とローマ教皇グレゴリウス7世が対立を始めます。
これが、聖職叙任権闘争です!
グレゴリウス7世はハインリッヒ4世が自分の主張を認めないため、破門します。
教皇からの破門されるということはその人は天国にはもう行けないということです。キリスト教を信じるものとしてそれほど恐ろしいものはないです。
さらに破門は、自身の権力をも揺るがします。つまり、教皇から祈ってもらえないような人間は皇帝としてふさわしくない!という意見が世間に蔓延し、帝国下の貴族たちの反乱を招く可能性があったのです。
ハインリッヒ4世は自分の皇帝としての権力を維持するために、グレゴリウス7世に破門の撤回を求めにアルプス山脈を越えます。
そして雪吹雪の中のカノッサ城で土下座して許しを請いた。これが有名な1077年のカノッサの屈辱です!
その後も皇帝・教皇間の争いは続き、1122年、ヴォルムス協約にて聖職叙任権は教皇が持つが、ドイツ領内では皇帝が承認権を持つという妥協案で、聖職叙任権闘争は終了します。
(ここまでだと教皇優位!な印象ですが、なんと破門を撤回してもらった皇帝ハインリッヒ4世は、数年後グレゴリウス7世に復讐しに帰って来て彼の右腕を切り落として追放します・・・)